「生活相談員の給料って低いんだよね・・・」
現場で働く人の中には、他職種との比較でこのような不安を感じる方が多くいらっしゃいます。
本記事は、介護業界で働く生活相談員やこれから生活相談員と目指す方に向けて、
給料の実態や低いと感じる背景、その改善方法をわかりやすく解説します。
生活相談員の給料アップの具体策やキャリア選択のヒントとなれば嬉しいです。

【この記事の著者について】
・現役の福祉施設職員
・2級FP技能士(2025年3月取得)
・2018年10月に株式投資をスタート!
・投資のスタイル:長期保有(バイアンドホールド)が基本
・高配当銘柄が大好き!株主優待も大好き!
・「社会福祉士が成年後見人を目指すブログ」を運営中
1. 生活相談員の給料は本当に低い?現状を把握しよう
生活相談員は、高齢者介護施設で入所者や家族との調整役を担う重要な職種です。仕事内容は多岐にわたり、施設利用の契約や相談対応、他職種との連携など幅広い業務を行います。
平均年収は地域や勤務先によって異なりますが、全国平均は約300万円台前半とされ、介護職全体の中でも中程度の水準です。手取り額は税金や社会保険料を差し引くとさらに減り、生活水準に影響することもあります。
他の介護職との比較では、現場介護職より若干高い傾向がある一方、大きな差はない場合も多いです。まずは、自分が目指す職場の給与体系や待遇を確認し、相場を把握することが大切です。
【職場比較】高齢者介護の仕事・職場タイプ別まとめ|給料・働きやすさを比較しました!

給料の違いを知っておくのも重要です!
1-1. 生活相談員とは?仕事内容と役割をおさらい
・利用者や家族からの相談対応・生活全般のサポート
・入退所や利用開始・終了時の手続き、関係機関との調整
・ケアマネジャーや医療機関、自治体などとの連絡・連携業務 等
生活相談員は、高齢者介護施設で入所者や利用者、その家族からの相談に応じる専門職です。入所や通所に関する契約手続き、サービス内容の説明、苦情や要望の対応など、利用者と施設をつなぐ役割を担います。
また、介護職員や看護師、ケアマネジャーなど多職種と連携し、利用者が安心して過ごせる環境を整える調整業務も重要です。
さらに、行政や地域包括支援センターとのやり取りを行い、必要な支援制度の利用につなげることもあります。生活相談員は現場介護を行うこともあり、幅広い業務を通して利用者の生活の質向上に貢献する存在です。
1-2. 平均年収・手取り額の相場は?【最新データあり】
生活相談員の常勤者における平均月収は約34万2,330円、中央値としての平均年収は約389万6,774円です。賞与も含めると、年間収入は360万〜410万円のレンジが多くなります。
手取り額は、月収34万円から約7〜8割を見積もって、およそ25万円前後が相場となります。雇用形態や地域、施設による差が大きいため、数値はあくまで目安として押さえておきましょう。
参考文献「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」
1-3. 他の介護職との給料比較で見えること
| 職種 | 平均月給(常勤) | 年収の目安 | 特記事項・他職種との差 |
|---|---|---|---|
| 生活相談員 | 約 ¥353,950 (レバウェル介護求人) | 約 ¥4,240,000前後(+手当含む) (tocotoco) | 介護福祉士より月給で若干上。ケアマネジャーには届かない水準 (レバウェル介護求人) |
| 介護福祉士 | 約 ¥331,080 (介護・福祉の求人・転職ならマイナビ介護職≪公式≫) | 約 ¥4,000,000前後(手取りはこれより若干低め) (介護・福祉の求人・転職ならマイナビ介護職≪公式≫) | 生活相談員と比べると手当や役職付きで伸びがあるが、同じくらいの施設形態・地域だと差は小さいことも多い (レバウェル介護求人) |
| ケアマネジャー(介護支援専門員) | 約 ¥388,080 (レバウェル介護求人) | 約 ¥4,600,000前後 (介護・福祉の求人・転職ならマイナビ介護職≪公式≫) | 生活相談員より高い給与水準。ケアプラン作成など責任範囲の広さが反映されることが多い (レバウェル介護求人) |
生活相談員の平均給与は月額約35万4,000円で、介護福祉士よりやや高めです。
一方で、ケアマネジャーの平均給与はさらに高く、生活相談員との差が見られます。
これは業務内容や求められる資格・責任範囲の違いによるもので、特にケアプラン作成など高度な業務には報酬差が反映されます。
ただし、生活相談員は相談・調整業務を通じて施設運営に不可欠な役割を担っており、専門性が評価されています。職種ごとの給与差を理解することで、自身のキャリア選択や資格取得の方向性を検討する参考になります。
この比較は、介護業界での将来的な収入見通しを立てるうえでも重要な視点となります。
ケアマネジャーの「給料事情」を記事にまとめました!
1-4. 給料の内訳|基本給・手当・ボーナスの実態
生活相談員の給与構成は、基本給に加えて職務手当や資格手当、通勤・住宅・扶養など多様な手当が含まれます。
例えば、常勤生活相談員の平均月給は342,330円で、そのうち基本給は214,470円です。
さらに、ボーナスは平均338,520円程度支給される傾向があります。
これらの内訳を把握することで、給与の全体像や転職時のチェックポイントが明確になります。
生活相談員の手当ってどうなってるの?給料に上乗せされる5つの支給項目を徹底解説!
2. なぜ生活相談員の給料は低いと言われるのか?
生活相談員の給与が低いと言われる背景には、「介護報酬に上限がある」制度的制約があります。
また、相談業務に必要な専門性が社会的に十分評価されていないことも理由の一つです。
さらに、介護施設自体の多くが赤字経営であり、報酬から賃金に回せる余裕が限られている現実があります。
こうした構造的な要因が重なり、生活相談員に限らず介護職全体の給料が上がりにくい状況が続いているのです。
・独立行政法人福祉医療機構(WAM)の調査について
「2023年度 通所介護の経営状況について」
2-1. 賃金体系や評価制度の問題
介護業界の賃金体系は事業所や法人ごとに設定が異なり、全国的に統一された基準がありません。
生活相談員は利用者や家族との調整業務など重要な役割を担いますが、その成果を定量的に評価する仕組みが整っていない施設も多くあります。
人事評価制度を導入していても、評価基準が曖昧で、実績やスキルが給与や賞与に十分反映されないケースが見られます。
また、基本給よりも手当や一時金に依存する給与構造の場合、長期的な収入増加が見込みにくい傾向があります。
こうした賃金体系や評価制度の課題は、生活相談員の給与が低く感じられる要因の一つとなっています。
2-2. 介護報酬制度の影響
介護職員の給与水準は、介護報酬制度によって大きく左右されます。
介護報酬は国が定めるサービス単価であり、事業所の収入源の大部分を占めます。
生活相談員は加算対象となる業務を担うこともありますが、その評価が直接給与に反映される仕組みは限られています。
また、報酬改定は3年ごとに行われますが、全体の増額幅が小さい場合、給与改善の余地も限られます。
さらに、加算要件の複雑化や事務負担の増加が経営を圧迫し、給与原資に回せる割合が減少する事業所もあります。
このように介護報酬制度の枠組み自体が、生活相談員の給与水準に影響を与える要因となっています。
2-3. 地域や法人による差が大きい現実
生活相談員の給与は、地域や運営法人の規模によって大きく異なります。
都市部では物価水準や人材確保競争の影響で比較的高い傾向があります。
一方、地方では介護報酬の範囲内で賃金を抑える事業所が多く見られます。
また、社会福祉法人や大手法人は手当や賞与が充実している場合があります。
しかし、小規模事業者や民間経営では基本給や昇給幅が低めに設定されることもあります。
このような地域差・法人差は、同じ職種でも生涯賃金に大きな影響を与えます。
転職や就職を検討する際には、地域の相場や法人の待遇制度を確認することが重要です。
2-4. 勤務年数や経験が反映されにくい理由
生活相談員の給与は、勤務年数や経験が十分に反映されにくい傾向があります。
その背景には、介護報酬の上限や法人内の賃金テーブルの制約があります。
多くの事業所では、経験年数に応じた昇給幅が非常に小さい状況です。
また、成果や業務量が評価基準に組み込まれにくい制度も影響しています。
資格を追加取得しても、基本給や手当の増額が限定的な場合があります。
そのため、長く勤務しても給与の伸びは緩やかで、モチベーション低下を招くこともあります。
処遇改善加算の配分方法によっては、経験者より全職員に均等配分されるケースもあります。
3. 昇給やボーナスの仕組みを知っておこう
生活相談員の昇給やボーナスは、勤務先の規模や法人の経営状況に大きく左右されます。昇給は年1回実施する事業所が多く、額は月数百円から数千円程度が一般的です。ボーナスは夏冬の年2回支給が主流ですが、基本給の低さが総額に影響します。
また、介護職員等処遇改善加算の配分により一時金が上乗せされる場合があります。
ただし、配分方法や評価基準は法人ごとに異なり、安定性にはばらつきがあります。
資格取得や役職就任などで職務範囲を広げることが、昇給額増加につながります。
制度の仕組みを理解し、自身の評価項目を把握することが収入向上の第一歩です。
【介護・社会・精神保健】3つの福祉士の給料・ボーナス事情を解説します
3-1. 昇給のタイミングと金額の目安
生活相談員の昇給は多くの施設で年1回、4月または7月に行われます。
昇給額は月額で500円から5,000円程度と幅があり、法人の経営状況に依存します。
また、昇給の有無や金額は人事評価や勤続年数、資格の有無などで左右されます。
評価制度が明確な法人では、成果やスキル向上が昇給額に直結する傾向があります。
一方、評価基準が不透明な職場では、昇給額が一定でモチベーションに影響します。
近年は介護職員等処遇改善加算の活用により、昇給に上乗せされる事例もあります。
自身の昇給条件や法人の方針を把握することが、安定的な収入増の第一歩です。
3-2. ボーナス(賞与)はどれくらいもらえる?
生活相談員のボーナスは、年2回(夏・冬)支給される法人が一般的です。
支給額は年間で基本給の1.5〜3か月分程度が目安とされています。
ただし、経営規模や財務状況により支給額は大きく異なるのが現実です。
介護職員等特定処遇改善加算の影響で、ボーナスに上乗せされる事例もあります。
一方、経営が厳しい施設では支給なし、または寸志程度の場合もあります。
賞与の有無や額は就業規則や労働契約書に明記されている場合が多いです。
転職を検討する際は、過去数年分の支給実績を確認することが重要です。
3-3. 手当や福利厚生で補える部分とは?
生活相談員の給与は基本給だけでなく、各種手当や福利厚生も含めて評価されます。
主な手当には資格手当、役職手当、通勤手当、住宅手当などがあります。
また、夜勤や早出は少ない職種ですが、特殊業務手当が支給される場合もあります。
福利厚生では、退職金制度や研修費用補助、健康診断などが代表的です。
法人によっては育児・介護休業の充実やリフレッシュ休暇の導入もあります。
こうした手当や制度は月収や年収を補い、働きやすさにも直結します。
転職や就職活動時には、給与額だけでなく福利厚生面も確認が必要です。
>>生活相談員の手当ってどうなってるの?給料に上乗せされる5つの支給項目を徹底解説!
4. 給料アップを目指す方法とは?
生活相談員が給料アップを目指すには、資格取得やスキル向上が有効です。
特に介護支援専門員や「社会福祉士などの資格」は給与反映の可能性があります。
また、法人内での役職昇進を目指すことも収入増につながります。
転職活動では、地域や法人規模による給与差を事前に把握することが重要です。
さらに、処遇改善加算の高い事業所を選ぶことで待遇向上が期待できます。
日々の業務で成果を積み上げ、評価制度に沿って自己アピールする姿勢も大切です。
このように複数の手段を組み合わせることで、安定的な収入増が可能になります。
【社会福祉士】働きながら取得した経験談
4-1. 資格取得で給料は上がるのか?
介護業界では、資格取得が給料に直結するケースが多く見られます。
特に「介護福祉士」や「社会福祉士」は資格手当が支給される場合があります。
また、「介護支援専門員(ケアマネジャー)」取得で基本給が上がる事例もあります。
法人によっては複数資格所持者に対し手当を加算する制度もあります。
ただし、資格を取っても評価制度や予算状況により反映幅は会社によって異なります。
資格取得にかかる費用を補助する制度が会社にあれば活用して負担を減らせます。この機会に確認されてはいかがでしょうか?
このように資格は昇給や手当増額の可能性を広げる有効な手段です。
4-2. 管理職やリーダー職を目指すキャリアアップ
介護現場でのキャリアアップには、管理職やリーダー職を目指す道があります。
施設長やサービス提供責任者などは、基本給や手当が大きく増える傾向です。
役職に就くと人材管理や業務全体の運営を担う責任も増します。
そのためマネジメントスキルや関連法規の知識が求められます。
法人によっては管理職登用に必要な研修や試験制度を設けています。
経験年数や勤務実績が昇進の条件に含まれる場合も少なくありません。
キャリアアップは収入増とやりがい向上の両面で有効な選択肢です。
4-3. 給料が高い職場への転職も視野に
介護職の給与は、施設形態や運営法人によって大きく差があります。
特に特別養護老人ホームや医療法人運営施設は比較的高水準です。
また、都市部や人材不足が深刻な地域では給与設定が高い傾向です。
転職活動では求人票だけでなく賞与や各種手当の有無も確認が必要です。
離職率や人員配置などの職場環境も長期的な勤務継続に影響します。
ハローワークや求人サイト、転職エージェントを活用すると効果的です。
待遇改善を目的とした転職は、収入と生活の安定につながります。
4-4. 副業で収入を補うという選択肢
生活相談員の収入を補う方法として、「副業」という選択肢があります。
在宅でできる「ライティング」や「データ入力」また、生活相談員のスキルが活かせる講師業など、本業に支障をきたさない範囲で選べる仕事が多様化しています。
副業を始める際は、勤務先の就業規則で禁止されていないか確認する必要があるなどいくつか注意点はありますが、収入を増やす有効な手段であることは間違いありません。

本業の経験・スキルを活かせる副業があるんです!
5. 将来の収入はどうなる?生活相談員のキャリア展望
生活相談員の将来の収入は、介護業界の制度改正や需要動向に左右されます。高齢化の進行により相談業務の需要は増加傾向にありますが、給与水準は介護報酬や施設運営の収益状況に依存するのが現状です。
キャリアを積むことで管理職や施設長などへの昇進が可能となり、役職手当等の増加で収入アップにつながる場合があります。
また、福祉系資格の取得をすることで地域包括支援センター勤務が可能になるなど、幅広い分野での活躍が将来の安定収入を確保する手段となります。
生活相談員のスキルアップ・給与アップを狙える資格とは?
生活相談員として経験を積んだあと、収入やキャリアの幅を広げるために有利な資格を
- 介護支援専門員(ケアマネジャー)
→ 給与水準が生活相談員より高い。業務の幅も広がる。実務経験と試験合格が必要。 - 主任介護支援専門員
→ ケアマネジャーの上位資格。地域包括支援センターなどでのキャリアにもつながる。 - サービス管理責任者(サビ管)/児童発達支援管理責任者(児発管)
→ 障害分野への転職や事業所運営などにも活かせる資格。給与アップの可能性も大。
【ケアマネジャーの手当】基本給だけじゃない!収入アップの仕組みと実態を解説
5-1. 勤続年数とともに給料は上がる?
生活相談員の給与は、勤続年数の増加によって必ずしも大幅に上がるとは限りません。
多くの施設では毎年わずかな昇給制度がありますが、その額は年数千円程度の場合もあります。
一方で、勤続年数が長くなることで役職や責任ある業務を任され、
役職手当や管理職手当が加算されることで収入が上がるケースも存在します。
ただし、介護報酬や法人の財政状況によって昇給幅は大きく変わります。
そのため、安定的な昇給を望む場合は法人の評価制度や昇進ルートを事前に確認することが重要です。
また、資格取得やスキル向上を組み合わせることで、勤続年数に加えて給与アップの可能性が広がります。
6. まとめ|生活相談員の給料事情を正しく理解しよう
生活相談員の給与は、介護職の中では中間的な水準に位置しています。
基本給に加え、各種手当やボーナスが収入を支える一方、
介護報酬制度や法人の賃金体系によって昇給幅や支給額は異なります。
また、地域差や勤務先の規模による影響も大きく、同じ職種でも収入に差が出ます。
安定した給与アップを目指すには、資格取得や管理職への昇進、
給与水準の高い職場への転職など複数の選択肢を検討することが有効です。
将来の収入見通しを把握し、長期的なキャリア設計を行うことで、
生活の安定とやりがいの両立が可能になります。
6-1. 現実を知り、今できる工夫から始めよう
生活相談員として安定した収入を得るには、現状の課題を正しく理解することが大切です。
賃金体系や介護報酬制度、地域差など、自分の給与に影響する要因を把握し、
改善の余地がある部分から取り組むことが収入アップへの第一歩となります。
例えば、資格手当の対象となる資格取得や、勤務先で評価されやすい業務への積極参加、
副業や節税対策など、今すぐ始められる工夫も少なくありません。
現実を受け止めつつも、自ら行動を起こすことで将来の安定につながります。
6-2. 給料の不安を減らすための具体的アクション
給料に対する不安を減らすには、現状の可視化と計画的な行動が必要です。
まず給与明細や就業規則を確認し、手当や昇給の条件を正確に把握します。
次に、自身のスキルや資格が賃金にどう反映されているかを整理し、
不足している部分は研修や資格取得で補うことが有効です。
また、地域や法人による賃金差も考慮し、必要に応じて転職市場の情報収集を行います。
加えて、「副業」や「資産形成」などを行い複数の収入源を持つことで将来の安心度が高まることができます。

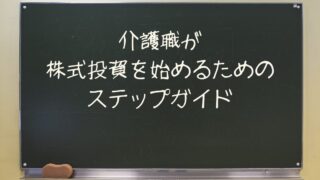

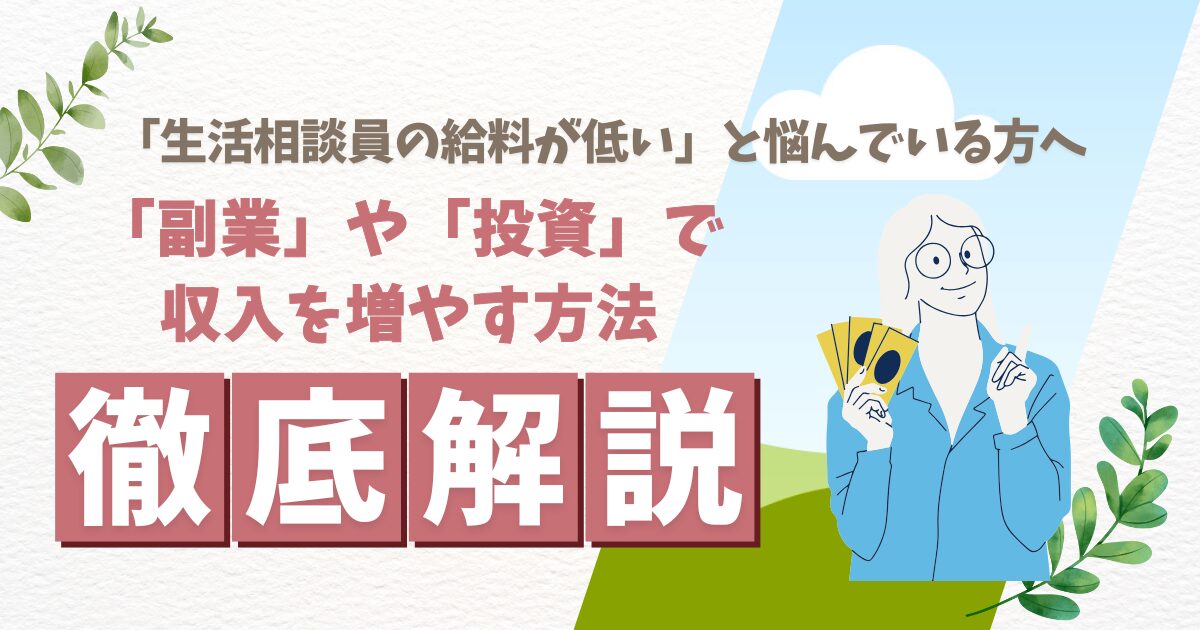







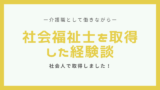


コメント