生活支援員として働いている方の中には、
「給料が安い」と感じている人も多いのではないでしょうか?
私自身も同じ悩みを抱えていました。
生活支援員の仕事は、障害のある方の生活を支えるやりがいのある仕事ですが、
給与面では他の業界で比べると、残念ながら厳しい現実があると思います。

【この記事の著者について】
・現役の福祉施設職員
・2級FP技能士(2025年3月取得)
・2018年10月に株式投資をスタート!
・投資のスタイル:長期保有(バイアンドホールド)が基本
・高配当銘柄が大好き!株主優待も大好き!
・「社会福祉士が成年後見人を目指すブログ」を運営中
生活支援員の平均給料について
厚生労働省のデータによると、生活支援員の平均月収は約20万円前後で、ボーナスを含めた年収は300万円程度が一般的です。これは他の福祉職と比較しても決して高いとは言えません。また、夜勤手当がつく場合もありますが、それを含めても大幅な収入増加は見込めないのが現状です。
なぜ生活支援員の給料は安いのか?
生活支援員の給料が安い背景には、いくつかの構造的な理由があります。
まず、福祉施設の多くは国や自治体の補助金で運営されています。
利益を上げづらいため、職員の給与に充てられる予算が限られているのです。
また、限られた人件費の中で運営するため、大幅な昇給も難しいのが現実。
さらに、無資格・未経験でも働ける職種であることも一因とされています。
専門性の高い職種と比べると、賃金が抑えられやすい傾向があります。
制度の見直しが求められていますが、現状では自己防衛が必要です。
公的な補助金に依存している
生活支援員が働く多くの施設は、国や自治体の補助金で成り立っています。
運営費の大部分が税金に依存しており、自由に使える予算が限られます。
そのため、収益を上げて職員の給料を増やすという仕組みが難しいのです。
また、施設の経営者側も人件費に多くを割けない状況が続いています。
補助金の配分基準は厳しく、事業所ごとの差が出にくいのも現実です。
公的な制度に守られている一方で、柔軟な給与改善が難しい背景があります。
この構造が、生活支援員の給料の上がりにくさに直結しているのです。
人件費の制約
福祉施設の運営費には限りがあり、人件費に回せる予算も限られています。
多くの施設は収益性が低いため、職員の給料を大きく上げるのが難しい状況。
人件費を増やすと経営が圧迫され、職員数の維持すら困難になることも。
結果として、現場で働く支援員の給与水準は低く抑えられがちです。
さらに、昇給やボーナスもごくわずかで、将来的な収入アップも望みにくい。
利用者支援の質を保ちつつ、限られた予算でやりくりする現実があります。
こうした構造的な制約が、給料の伸び悩みにつながっているのです。
資格の有無
生活支援員の仕事は、無資格や未経験でも始められることが特徴です。
そのため、専門性の高い職種と比べて給与が低く抑えられる傾向があります。
採用のハードルが低い一方で、スキルや知識に対する評価が見えにくいのが実情。
資格がないことで、手当の対象外になるケースも多く存在します。
一方で、介護福祉士や社会福祉士などの資格を取得すれば評価は変わります。
資格があると手当が支給されたり、昇進やキャリアアップにもつながります。
将来を見据えて、計画的に資格取得を目指すことが収入アップの鍵です。
給料が安いと悩んだ私が取り組んだこと
生活支援員として働く中で、将来の収入に不安を感じるようになりました。
現場はやりがいがある反面、給料面ではどうしても限界があります。
このままでは生活が厳しくなると感じ、できることから始めてみました。
まずは休日やスキマ時間を活用し、副業に挑戦して収入の柱を増やしました。
さらに、資格取得や資産運用など、長期的に効果が見込める方法も実践。
収入源を複数持つことで、気持ちにも余裕が生まれるようになりました。
「何もしないより、小さくても一歩踏み出すこと」が大切だと実感しています。
副業を始めた
生活支援員の仕事はシフト制で、休日や空き時間を確保しやすい働き方です。
この特性を活かして、副業に挑戦することを決意しました。
最初は自宅でできるライティングやアンケートモニターから始めました。
本業の負担にならない範囲で取り組めるため、継続しやすかったです。
少しずつ収入が増えることで、気持ちにもゆとりが生まれました。
副業は収入面だけでなく、自分のスキルや視野を広げるきっかけにもなります。
「時間がない」と諦めず、できることから始めるのが成功のコツだと感じました。
ブログ運営を開始!
副業の一つとして、自分の経験を活かせるブログ運営を始めました。
生活支援員としての働き方や給料事情など、リアルな情報を発信しています。
記事を書き続けることで、読者の役に立てるというやりがいも感じました。
最初は収益ゼロでしたが、少しずつアクセスが増えて成果が出てきました。
広告収入やアフィリエイトを通じて、月数千円〜1万円の収入に成長中です。
パソコン一つで始められ、文章が苦手でも継続すれば形になります。
福祉の現場で感じたことを、情報として届ける手段としても有効です。
資産運用を活用した!
生活支援員の収入だけでは将来に不安を感じ、資産運用を始めました。
最初は少額から始められる「つみたてNISA」で、コツコツと投資を継続。
給与の一部を毎月自動で積み立てることで、無理なく続けられています。
大きな利益はすぐに出ませんが、長期で見れば安定した資産形成が可能です。
また、投資信託を中心に選ぶことで、知識がなくても運用しやすい点も魅力。
「お金にも働いてもらう」感覚が身につき、金銭的な安心感が少しずつ増えました。
将来の備えとして、収入の一部を投資に回すことは有効な選択肢だと感じています。
>>「いきなり投資は怖い・・・」という方はこちらの記事がおすすめ
手当が支給される資格を取得した!
収入を少しでも増やすために、手当がつく資格の取得に挑戦しました。
私が選んだのは業務に直結し、現場でも役立つ「中型自動車免許」です。
マイクロバスの送迎業務が可能になり、資格手当や勤務の幅が広がる効果がありました。
資格の取得には時間と費用がかかりますが、長期的には費用対効果は十分。
他にも、介護福祉士やサービス管理責任者なども手当対象になることが多いです。
自分の強みを増やすことで、給料アップとキャリアアップの両方を狙えます。
中型免許を取得した!
施設での送迎業務にも対応できるよう、中型自動車免許を取得しました。
送迎車の運転を任されるようになり、資格手当も支給されるように。
業務の幅が広がることで、職場内での信頼や役割も大きくなりました。
免許取得には一定の費用がかかりますが、長期的には十分元が取れます。
とくに地方の福祉施設では送迎業務が必須の場面も多く、重宝されます。
給与アップだけでなく、職場での活躍の場を増やす選択肢にもなります。
まとめ
「生活支援員の給料が安いからどうしようもない」と諦めるのではなく、
副業・節約・投資・資格取得を組み合わせることで、
少しずつ収入を増やすことができます。
特に、ブログやライティングなどの副業は時間をかければ収益化できる可能性が高く、
将来的に安定した収入源になるかもしれません。
また、スキルアップによるキャリアアップも選択肢の一つです。
大切なのは「できることから始める」ことです。
まずは小さな一歩から、将来のために行動を起こしてみてください!

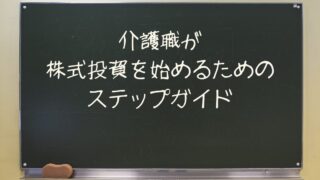


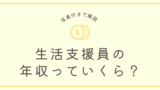


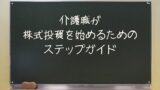

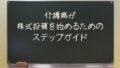
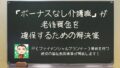
コメント