
【この記事の著者について】
・現役の福祉施設職員
・2級FP技能士(2025年3月取得)
・2018年10月に株式投資をスタート!
・投資のスタイル:長期保有(バイアンドホールド)が基本
・高配当銘柄が大好き!株主優待も大好き!
・「社会福祉士が成年後見人を目指すブログ」を運営中
1. 生活支援員と相談支援専門員、どちらが稼げるのか?

福祉の現場で働くなかで、「もっと収入を増やしたい」と感じる人は少なくないですよね。
障害者支援に携わる代表的な職種に「生活支援員」と「相談支援専門員」があります。
「一体どちらが稼げるのか?」気になる人も多いと思います。
この記事では、両職種の平均年収や手当の違い、昇給の可能性などを比較して解説します。
それぞれの職種の特徴をふまえながら、自分にとってより収入面で有利な働き方を見つけるヒントを紹介します。
【障害者施設】生活支援員の年収はいくら?
1-1. それぞれの職種の基本情報と違い
| 項目 | 生活支援員 | 相談支援専門員 |
|---|---|---|
| 主な役割 | 障害のある人の日常生活を支援する | 障害のある人や家族の相談に応じ、支援計画を作成する |
| 主な業務内容 | 食事・入浴・排せつなどの介助、生活全般の支援 | 支援計画(サービス等利用計画)の作成、関係機関との調整 |
| 活動の場 | 現場中心(施設・グループホームなど) | 相談支援事業所など |
| 役割の違い | 支援の「実施」を担う | 支援の「計画」を担う |
生活支援員と相談支援専門員は、どちらも福祉分野で重要な役割を担う職種です。
生活支援員は、障害のある人の日常生活を支える現場中心の仕事です。
具体的には、食事・入浴・排せつなどの介助や、生活全般の支援を行います。
一方、相談支援専門員は、障害のある人や家族からの相談に応じ、支援計画の作成や関係機関との調整を担います。
支援の「実施」と「計画」で役割が異なる点が大きな違いです。
1-2. 平均月収・年収の比較
生活支援員と相談支援専門員の収入には、明確な違いがあります。
生活支援員の平均月収は約20万円前後、年収ではおおよそ300万円前後が目安です。
一方、相談支援専門員は月収22万〜25万円程度で、年収は350万円〜400万円が一般的です。
ただし、地域差や勤務先によって収入には幅があります。
どちらも資格や経験によって収入アップが見込めますが、相談支援専門員のほうがやや高い傾向です。
生活支援員の給料の実態とは?

生活支援員として働く私が給料事情を解説しました
相談支援員の給料の実態とは?
1-3. 賞与(ボーナス)や各種手当の違い
賞与や手当の面でも、生活支援員と相談支援専門員には違いがあります。
生活支援員は、夜勤手当や処遇改善手当が支給される職場が多く見られます。
相談支援専門員は、資格手当や役職手当がつく場合があり、支援計画作成に応じた報奨金制度がある事業所もあります。
賞与はどちらも年2回支給されることが多いですが、勤務先によって金額や支給実績に差があります。
就職前に確認することが大切です。
1-4. 昇給・キャリアアップの可能性

昇給やキャリアアップのしやすさにも、職種ごとの特徴があります。
生活支援員は、「リーダー」や「サービス管理責任者」などを目指すことで収入が上がります。
一方、相談支援専門員は、実績を積むことで「主任相談支援専門員」への昇格が可能です。
いずれも資格取得や研修の受講が昇給に直結する場合があります。
現場経験に加えて専門性を高めることで、キャリアの幅を広げられる点が共通しています。
2. どちらが安定して働ける?将来性と雇用環境の比較
収入だけでなく、安定して長く働けるかどうかも重要な判断材料です。
生活支援員は常勤・非常勤を問わず求人が多く、現場ニーズが高い職種です。
一方、相談支援専門員は配置が義務づけられている施設もあり、専門性の高い人材が求められています。
いずれも福祉制度の継続によって需要が見込まれますが、働き方や雇用条件に違いがあります。
将来を見据えた選択が安定につながります。
2-1. 求人の多さ・ニーズの高まり
生活支援員と相談支援専門員は、いずれも福祉分野で高いニーズがあります。
生活支援員は、入所施設やグループホームでの求人が安定して多いのが特徴です。
相談支援専門員は、障害福祉サービス計画の作成が義務づけられているため、
専門職としての需要が増えています。高齢化や障害者支援の拡充により、両職種とも今後も求人数の増加が予想されます。
2-2. 雇用形態と労働条件の違い
生活支援員と相談支援専門員では、雇用形態や働き方に違いがあります。
生活支援員は正職員・パート問わず募集が多く、夜勤やシフト勤務が一般的です。
相談支援専門員は日勤中心で、正職員としての採用が多く見られます。
生活支援員は身体介助を伴うため体力的な負担が大きく、労働時間が不規則になりがちです。
相談支援専門員は対人援助が中心で、書類業務や外出が多い点が特徴です。
2-3. 長期的に収入が伸びるのはどっち?
生活支援員と相談支援専門員では、収入の伸び方にも差があります。
生活支援員は経験を積むことで昇給や役職手当が期待できますが、収入の上限は比較的早く頭打ちになる傾向です。
相談支援専門員は、主任相談支援専門員など上位資格へのステップアップが可能です。
専門性を高めることで収入の幅が広がる点が特徴です。
長期的に見ると、相談支援専門員のほうが収入が伸びやすいとされています。
3. 資格取得にかかる費用とリターン

生活支援員と相談支援専門員では、資格取得に必要な費用や負担が異なります。
生活支援員は特別な資格がなくても働けますが、介護福祉士などの資格取得で手当や昇給の対象になります。
相談支援専門員は、実務経験に加えて相談支援従事者初任者研修の受講が必須です。
研修には数万円の費用がかかることもありますが、取得後は専門職として待遇が上がるケースが多く、投資に見合う価値があります。
3-1. 生活支援員に必要な資格とコスト
生活支援員は、無資格でも働ける職場が多く、ハードルは比較的低めです。
ただし、介護福祉士や初任者研修を取得することで、待遇が改善されやすくなります。
初任者研修は5万〜10万円程度の費用がかかり、通学や通信での受講が可能です。
介護福祉士を目指す場合は実務経験が必要で、試験対策講座などの費用も発生します。
資格を取得することで、昇給や正職員採用につながる可能性があります。
3-2. 相談支援専門員に必要な資格と研修制度
相談支援専門員として働くには、一定の実務経験と研修受講が必要です。福祉・介護・医療分野での実務経験が5年以上あることが主な条件とされています。
加えて、「相談支援従事者初任者研修」の修了が必須です。
この研修は自治体や研修機関が実施し、費用は3万〜5万円程度が一般的です。
研修では制度の基礎や支援技術を学び、修了証を得ることで正式に従事できるようになります。
4. 「もっと稼ぎたい」あなたに伝えたい現実
生活支援員や相談支援専門員として働く中で、収入面に限界を感じる人も少なくありません。
現場の仕事はやりがいがある一方で、年収の大幅な上昇は難しいのが実情です。
資格を取得しても、昇給や手当の伸び幅には上限があります。
副業や転職による収入アップも選択肢の一つですが、時間的な余裕が必要です。
もっと稼ぎたいなら、現職にこだわらず、柔軟な働き方を考えることも重要です。
4-1. 福祉職は努力しても収入に限界がある

職種を変えても収入が大きく増えないなら、
結局どうすれば収入って上がるの…?

福祉職は収入の伸びが緩やかなので、
副業などで収入源を増やすのが現実的です。
福祉職は社会的意義が大きい反面、収入面では限界があるのが現実です。
経験を積んでも昇給幅は小さく、年収が大きく伸びることは稀です。
資格取得や役職昇格で手当は増えますが、基本給の大幅な上昇は期待しにくい状況です。
国や自治体の制度に左右されるため、個人の努力だけでは収入を伸ばしづらい側面があります。
安定性はあるものの、「稼ぐ」という観点では難しさがあります
4-2. 副業で収入を増やす選択肢
福祉職の収入に限界を感じたとき、副業は現実的な選択肢となります。
本業に支障が出ない範囲で、スキマ時間を活用した副業が注目されています。
ブログ運営やライティング、資格を活かした講師業などが人気です。
在宅でできる副業は体力的な負担が少なく、福祉職との両立もしやすいのが特長です。
最初は小さな収益でも、継続することで収入源として育てることが可能です。

収入源を増やせれば生活の不安が減りますよね!
福祉職におすすめの副業5選!
| おすすすめ順位 | 副業名 | 向いてる人 |
|---|---|---|
| 1位 | ブログ | 文章が好きな人 |
| 2位 | ココナラ | 話すのが得意な人 |
| 3位 | YouTube | 発信好きな人 |
| 4位 | ポイ活 | 継続が得意な人 |
| 5位 | 投資 | コツコツ型の人 |
4-3. 資格と経験を活かしてブログ収益を得る方法
福祉職は日頃から経験を言語化しているため

長年の経験で得た知識や日々の支援の工夫は、
多くの人の役に立つんです!
福祉職での資格や経験は、ブログ収益化の大きな強みになります。
現場で得た知識や体験を記事にすることで、読者の共感や信頼を得やすくなります。
介護や支援のノウハウ、仕事の悩みなどは検索ニーズが高く、アクセスにつながりやすい分野です。
広告収入やアフィリエイトを組み合わせれば、継続的な収益も可能です。まずは無料ブログから始め、少しずつ発信の幅を広げることが大切です。
福祉業界で働く方へ!知識と経験を活かせるブログ副業のすすめ
5. ブログで収益を得るまでのステップ【福祉職向け】

私は以下の書籍を参考にしてブログの開設作業を進めました!
福祉職の知識や経験を活かし、ブログで収益を得ることは十分可能です。
まずは自分の得意分野や書けるテーマを整理し、読者の悩みに応える記事を意識します。
無料または有料ブログサービスを利用し、記事を継続的に投稿していきます。
アクセスが集まり始めたら、広告やアフィリエイトを設置して収益化を目指します。
地道な更新と信頼性のある内容が、収益につながる鍵となります。
5-1. ブログがなぜ稼げるのか?仕組みを解説
ブログが稼げる理由は、広告収入とアフィリエイトによる仕組みにあります。記事に訪れた読者が広告をクリックしたり、紹介した商品を購入することで報酬が発生します。
福祉職の経験をもとにした情報は信頼性が高く、読者の行動につながりやすいのが特徴です。アクセス数が増えるほど収益のチャンスも広がるため、
継続的な発信が重要です。知識と体験が収入になるのが、ブログの強みです。
5-2. 福祉職×ブログの成功パターンとは
福祉職とブログの相性は良く、成功パターンも確立されつつあります。実体験をもとにした記事は、同業者やこれから福祉業界を目指す人の関心を集めやすいです。
介護技術や資格取得のコツ、現場での悩みの対処法などは検索ニーズが高く、安定したアクセスにつながります。
特化ブログとして情報を積み重ねることで、信頼と収益の両方を得ることが可能です。継続が成功のカギとなります。
5-3. 今日から始めるブログ収益化の手順
ブログ収益化を始めるには、まずテーマとターゲットを明確にしましょう。
次に、無料か有料のブログサービスを選び、初期設定を行います。記事は福祉職の経験や知識に基づいた内容を中心に書くと効果的です。
アクセスが集まり始めたら、GoogleアドセンスやASPに登録し、
広告やアフィリエイトを設置します。焦らず継続することが、収益化への一番の近道です。
ブログの収益化の方法とは?初心者でもわかる仕組みと稼ぎ方を徹底解説【完全ガイド】
6. まとめ|「どちらが稼げるか」より「どう稼ぐか」へ
生活支援員と相談支援専門員、収入の差は確かに気になるポイントです。
ですが、職種を選ぶだけでは大きく稼ぐことは難しいのが現実です。
大切なのは、「どちらが稼げるか」ではなく「どう稼ぐか」を考える視点です。
本業に加え、副業やブログ運営など新たな収入源を持つことが収入安定のカギになります。
自分の強みを活かした工夫が、将来の選択肢を広げてくれます。
6-1. 福祉職の選択と収入の可能性
福祉職には多くのやりがいがありますが、収入面では限界を感じることもあります。
生活支援員か相談支援専門員かで迷う前に、「どう稼ぐか」に目を向けることが重要です。本業に加え、副業やスキルアップで収入の幅を広げる選択肢があります。
資格や経験を活かした発信や副収入づくりは、現実的で再現性も高い手段です。
職種に縛られず、柔軟に収入を築く姿勢が大切です。
6-2. あなたの経験が価値になる時代
今は、一人ひとりの経験や知識が収入に変わる時代になっています。福祉職での実体験や学びは、
同じ道を目指す人にとって貴重な情報です。
そうした経験をブログやSNSで発信することで、新たな価値が生まれます。
「どう稼ぐか」を考えたとき、あなたの体験そのものが武器になります。
専門性と継続があれば、経験は収益へとつながっていきます。

例えば、施設で経験した「ヒヤリハット」は、
他の施設で働く人にとっても参考になる場合が多いと思います
【障害者施設のヒヤリハット事例】支援場面別にまとめました!
6-3. 今こそ、ブログで収入アップの一歩を踏み出そう
安定収入を目指すなら、今こそブログを始める絶好のタイミングです。
福祉職で得た知識や経験は、他の誰かの役に立つ情報となります。
記事を書き続けることで信頼とアクセスが集まり、やがて収益に結びつきます。
「どう稼ぐか」を真剣に考えるあなたにこそ、ブログは強い味方になります。
今日から一歩を踏み出し、自分の価値をお金に変えていきましょう。

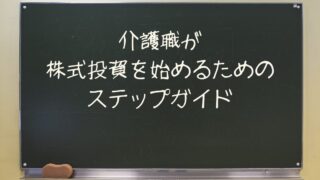


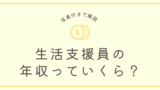







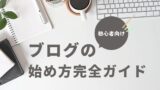


コメント